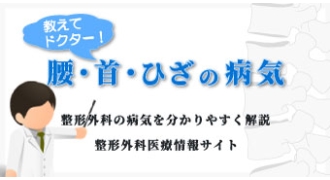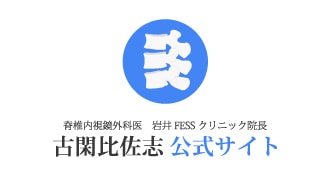2025年02月18日
福島県立医科大学
滋賀大学
岩井整形外科病院
東京医科大学
岩井医療財団岩井整形外科病院の富永亮司医師、滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センターの池之上辰義准教授、東京医科大学医療データサイエンス分野の田栗正隆主任教授、福島県立医科大学大学院医学研究科臨床疫学分野の栗田宜明特任教授を中心とする研究グループは、日本人骨粗鬆症患者を対象に、新しい骨粗鬆症治療薬と従来の治療薬に対して、心血管疾患(注2)の発生リスクを比較する研究を実施しました。その結果、新薬ロモソズマブ(注3)は、従来薬ビスフォスフォネート(注4)と比較して心血管疾患のリスクに大きな差がないことを明らかにしました。この研究成果は、ロモソズマブの心血管疾患のリスクが高くないことを示す経験的根拠を提供し、医療現場における治療選択に役立つものです。
【本研究成果のポイント】
- 新しい骨粗鬆症治療薬ロモソズマブは、開発段階から優れた骨折予防効果が報告されてきましたが、心血管疾患リスクの増加に関する懸念も指摘されていました。
- 研究グループは、日本の医療レセプトデータを用い、約6万人の骨粗鬆症患者を対象に、安全性比較を行いました。
- ロモソズマブと従来から広く使用されているビスフォスフォネートの使用開始後1年間における心血管疾患の発生リスクを解析した結果、両薬剤間で心血管疾患の発生率に大きな差が認められなかったことを実証しました。
Ⅰ.研究の背景
骨粗鬆症(注1)は、骨が弱くなり、転倒などの小さな衝撃でも骨折しやすくなる病気です。日本では40歳以上の推定患者数が約1590万人(男性410万人、女性1180万人)とされ、国民の約7.8人に1人が罹患しています。高齢化が進む中、この疾患への対策が急務とされています。
骨粗鬆症治療の新薬であるロモソズマブは、骨密度を大幅に改善する効果ある一方で、開発段階から心血管疾患のリスクを増加させる可能性が懸念されてきました。この課題に対応するため、研究グループは日本人の骨粗鬆症患者を対象に、ロモソズマブと従来から広く使用されているビスフォスフォネートを比較し、心血管疾患リスクの安全性を検証する研究を実施しました。
Ⅱ.研究の概要
本研究では、日本の医療レセプトデータ(注5)を用いて、骨粗鬆症または骨粗鬆症性骨折の診断を受けた40歳以上の患者約6万人を対象に解析を行いました。ロモソズマブまたはビスフォスフォネートを新規に処方された患者について、1年間の心筋梗塞や脳卒中の発生率を比較しました。
Ⅲ.研究の成果
本研究では、新たに治療を開始した患者を対象としたコホート研究デザイン(注6)を採用し、解析には因果推論の信頼性を高めるための「操作変数法」(注7)を用いました。この方法では、医療機関ごとのロモソズマブ処方率を操作変数として活用し、治療選択に影響を与える未測定の要因(交絡因子)を調整することで、より正確な結果を得ることが可能です。
解析の結果、ロモソズマブを使用した患者の1年間の心血管疾患発生率は12.3/100人年であり、従来薬であるビスフォスフォネートを使用した患者では11.4/100人年でした。これらのデータに基づくロモソズマブ使用の発生率比は1.08(95%信頼区間: 1.00–1.18)でした。一方、操作変数法を用いた解析では、ロモソズマブ使用のハザード比は1.30(95%信頼区間: 0.88–1.90)と推定され、ビスフォスフォネートと比較して心血管疾患リスクが大幅に増加する確固たる証拠は得られませんでした。
これらの結果は、ロモソズマブが心血管疾患リスクを大きく増加させる可能性は低いことを示唆しており、新規治療薬としての安全性を裏付ける重要なデータです。この知見は、医療現場での治療選択に役立つ経験的根拠になると期待されます。
Ⅳ.今後の展開
本研究の結果は、ロモソズマブの安全性を一定程度支持するものです。しかしながら、長期的な安全性についてはさらなる検証が必要です。今後は、データを活用した研究によるさらなる検証が期待されます。
Ⅴ.研究成果の公表
本研究成果は、2025年1月17日、科学誌「Journal of Bone and Mineral Research」に掲載されました。
- 論文タイトル: Comparative cardiovascular safety of romosozumab versus bisphosphonates in Japanese patients with osteoporosis: a new-user, active comparator design with instrumental variable analyses
- 著者: Ryoji Tominaga, Tatsuyoshi Ikenoue, Ryosuke Ishii, Kakuya Niihata, Tetsuro Aita, Tadahisa Okuda, Sayaka Shimizu, Masataka Taguri, Noriaki Kurita
- DOI: 10.1093/jbmr/zjaf010
【用語解説】
(注1) 骨粗鬆症
骨が弱くなり骨折しやすくなる病気。特に高齢者や女性に多く見られます。
(注2) 心血管疾患
心筋梗塞や脳卒中など、心臓や血管に関連する病気の総称です。
(注3) ロモソズマブ
新しい骨粗鬆症治療薬で、骨密度を高める作用を持っています。
(注4) ビスフォスフォネート
骨粗鬆症治療に広く使用されている薬剤で、骨が壊れるのを抑える作用があります。
(注5) 医療データ(レセプトデータ)
患者の診断、治療、薬の処方に関する情報を含む、医療機関が作成するデータです。
(注6) 新たに治療を開始した患者を対象としたコホート研究デザイン
この研究デザインは、薬剤が新たに処方されたすべての患者を対象とする方法です。これにより、副作用などの理由で治療を中断した患者も含めて評価することが可能となり、薬剤の安全性を現実に近い条件で比較することができます。
(注7) 操作変数法
操作変数法は、薬の効果を正確に評価するための統計手法です。この方法では、患者が治療を受けるかどうかを「間接的に決まる要因(操作変数)」を使って評価します。例えば、病院ごとに薬の使い方に違いがあり、ある病院では新しい薬ロモソズマブを積極的に使用し、別の病院ではあまり使わない場合、その違いを操作変数として利用します。
通常のデータ解析では、患者の年齢や健康状態などの特性が治療結果に影響を与えることがあります。このような影響が混ざると、「薬の効果」と「患者の特性」が区別できなくなり、薬の効果を正しく評価するのが難しくなります。特にレセプトデータを使った研究では、患者の詳細な情報がすべて揃っていないことが多く、「患者の特性」の影響が結果に反映されやすくなります。
操作変数法を使うことで、特定の条件が満たされると、このような影響を取り除き、より正確に薬の効果を評価することができます。これにより、ランダム化試験に近い形で、薬の効果を信頼性高く測定することが可能となります。
本件に関するお問い合わせ先
<研究に関すること>
公立大学法人福島県立医科大学 医療研究推進課 課長 菊地芳昇
TEL:024-547-1795
<取材に関すること>
医療法人財団 岩井医療財団 IT・広報部 広報課
TEL:03-6433-3063 メール:koho@iwai.com